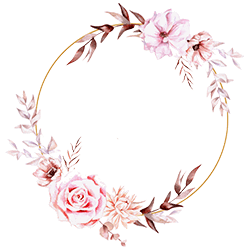2025.07.12
「未来を知りたい」と思った、その瞬間から——占いのはじまりを辿る旅

もし、いまの自分が選ぼうとしている道が正しいのか、
確かめられる方法があるとしたら——
そんな願いを、人はいつから抱いてきたのでしょうか。
占いのはじまりは、
信じたい気持ちと、恐れと、そして希望から生まれました。
それは遠い昔の出来事だけれど、
その“問いかける力”は、今も私たちの中に息づいています。
1. 紀元前2000年 メソポタミア——神の声は肝臓のかたちに
今から4000年以上前。
現在のイラク周辺、メソポタミア文明のバビロニア王国では、
「肝臓占い」が国家の重要な儀式とされていました。
捧げられた羊の肝臓のかたち、色、筋の入り方。
それらはすべて、神が人間に伝える“兆し”と考えられていたのです。
実際に王は、戦争や都市建設などあらゆる決断の前に、
必ず肝臓を見せ、「この先に災いはないか」を確かめました。
そして、それらの占い結果は粘土板に詳細に記録され、
占術師はそれを何年もかけて学び、読み解いていたのです。
占いは迷信ではなく、“国を守るための知識”だった。
未来を恐れながらも、前に進むための手段でした。
2. 紀元前8世紀 ギリシャ・デルポイ——答えは山の上にあった
神託(オラクル)を求めて旅をする人々がいました。
向かう先は、ギリシャ・パルナッソス山の中腹にある「デルポイの神殿」。
太陽神アポロンに仕える巫女が、神の声を伝える場所です。
神託を受けるためには、山を越え、順番を待ち、
「問い」を紙に書いて捧げなければなりませんでした。
そこには国王や将軍だけでなく、
恋に悩む若者や、家族を守りたいと願う市民の姿もあったと記録されています。
巫女は時に詩のような言葉で答えを伝え、
その意味を読み解くのは聞いた者の“心”に委ねられていました。
答えはひとつじゃない。
けれど「誰かが聞いてくれる」という安心が、
彼らを山へと向かわせたのかもしれません。
3. 15世紀 イタリア・ミラノ——美しいカードが「物語」を映し出す
15世紀中頃、イタリア・ミラノのヴィスコンティ家で、
とても贅沢な遊戯用のカードがつくられました。
それが、後の「タロットカード」です。
カードには「女帝」「死神」「星」「愚者」などの象徴が描かれ、
金や銀の装飾が施されていました。
当初は占いではなく、貴族の間で楽しまれる芸術的なゲームだったのです。
けれど18世紀になると、フランスの神秘主義者たちがこのカードに意味を見出し始めます。
「これは古代エジプトの叡智を継ぐものだ」
「人生の流れがこの中に描かれている」と——。
人々はカードの並びの中に、自分自身を重ねて読み始めたのです。
「今、自分はどこに立っているのか」
「何を手放し、どこへ進むべきか」
タロットは人生を写す“もうひとつの鏡”となり、
現在まで語り継がれていきました。
4. 現代——見えないものに問いを投げるということ
科学が進み、未来を予測する技術が生まれた今も、
人は完全に「安心」を手に入れたわけではありません。
将来のこと、人の気持ち、自分の進む道。
どれだけ知識が増えても、
最後の一歩を決めるのは、やはり“心”です。
そんなとき、昔の人たちのように——
なにかに問うてみたくなる瞬間がある。
空でもいい。
風の音でも、カードでも、誰かの言葉でも。
答えが書いてあるわけじゃないけれど、
“考えるきっかけ”がそこにある。
それが占いという文化が、何千年も途切れず残ってきた理由かもしれません。
占いは、未来を決めてくれるものではありません。
でも、「どうしたらいいか」と考える、その手がかりにはなってきました。
肝臓のかたちを読み、山の上で神の声を待ち、
カードに心を重ねる——
それはすべて、
“自分の人生を、自分の足で歩くために”
人がくり返してきた問いかけのかたちです。
今もどこかで、
その問いは静かに続いているのかもしれません。
Aliceホームにもどる
※当サイトの記事を引用・転載する場合には必ず、引用・転載元となる記事への有効なリンクを設置してください。
次のページ
![]() PAGE TOP
PAGE TOP